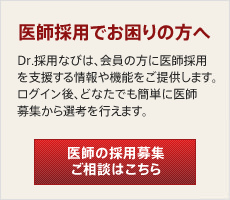Dr.採用なびは、医療機関の採用担当者向けのコミュニティサイトです。
- ようこそ!ゲストさん!
- ホーム >
- ロゴ・マークに込める医療の想い
2013.04.03
ロゴ・マークに込める医療の想い
ロゴマークに込める医療の理念:医療機関にふさわしいマークとは
東 昭吾(あずま しょうご)
NPO法人日本HIS研究センター 事務局員

|
はじめに |
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.医療機関のブランドイメージとは?
-----------------------------------------------------------------------------------------
| “CI”と“ブランディング” 企業などの場合、イメージ醸成のために“CI”という言葉が用いられます。CIとは、“Corporate Identity”の略で、企業の特性や独自性を、イメージやデザイン、わかりやすいキャッチフレーズ(コピー)などで表現し、社会(具体的には顧客や職員・マスコミ)に発信することで自らの存在価値を高めていく戦略です。 最近では、このイメージ醸成において、“顧客・消費者の信頼”を獲得することを特に重視した“ブランディング”といった言葉で表現する場合もあります。 こうした戦略は企業に限ったことではなく、利用者(患者さん)との信頼が最も大切な医療機関においても、大いに経営戦略に取り込んでおきたい概念です。
医療機関のブランドとは? 企業が提供する商品やサービスの場合、顧客の心理状態を考えると不安を感じている状態で購入・利用するということはまずありません。普通は、ほしい商品やサービスが手に入るという期待の方が大きいでしょう。 ところが、特に患者さんの場合、自分の身体や心について、少なからず不安を抱きながら医療機関を訪れるのが普通です。このため、同じイメージ醸成といっても、企業と医療機関とでは、自ずと注意すべき点が異なります。 もちろん、医療において利用者(患者さん)の不安をすべて取り除くことは難しいですが、少しでも不安を少なくするための努力や対応が「一貫して感じられた」とき、利用者(患者さん)は安心感を覚え、その医療機関に対し全幅の信頼を抱くことになります。 つまり、医療機関にとって特に大切なイメージ醸成の手はじめは、“不安を安心感に変えること”なのです。こうしてつくられる全幅の信頼感が医療機関における「ブランドイメージ」であり、企業の商品・サービスに対する信頼とは性質が異なります。  ここで自覚しておいてほしいことは、医師や看護師をはじめとする職員が考えている以上に、利用者(患者さん)は細かいところまで見ており、その印象が医療機関への信頼の判断材料になっているということです。例えば、アメリカのメイヨークリニックでは、「ナースの靴ヒモがゆるんでいる」ことを患者さんは見ているとして注意されるそうです。これは、“自分たちは見られている”“何気ないことが自分たちへの一貫したイメージを左右する”と気付いている好例でしょう。 こうした一貫したよいイメージを利用者(患者さん)に自ら感じてもらう(イメージアップ)ための有効な手段のひとつに、経営戦略の根幹である理念やイメージの“可視化”があります。 そこで、ロゴマークに理念を可視化した、ある医療機関の例をみていきましょう。 |
-----------------------------------------------------------------------------------------
2.視覚的イメージの要~ロゴ・マーク
-----------------------------------------------------------------------------------------
|
ロゴ・マークはイメージアップの重要要因 医療機関のイメージを決定する要因には、下図のように主に4つあります。当然、すべてに配慮が必要ですが、忘れてはならないのが、第一印象にその後の評価も左右されてしまう可能性が高いということです。
私たちは日ごろ、街中の看板やパンフレット、ホームページなど、さまざまな場面で何気なくロゴやマークを目にしています。好みにもよりますが、多くの人の印象に残り、好感がもてるマークというものがあります。こうしたマークがもつ人の目を引きつける力を、“誘目率”といいます。
ロゴとマークのポイントとは? ロゴ・マークは、将来にわたり医療機関の視覚的イメージすべてを統一する要であり、メッセージを伝える重要なシンボルです。このため、新しくロゴやマークを制定する際には十分な検討が必要で、ロゴ、マークそれぞれに見逃せない以下のようなポイントがあります。
マークの5Point!
新しいマークやロゴを決める機会は、理念の確認やマーク案の公募など、職員全員を巻き込んでイメージアップづくりができる絶好の機会です。その一方で、マーク案の評価や最終的な決定方法、そしてさまざまなポイントに配慮したデザイン処理などには、専門的な知識と経験が必要となります。 デザインの展開にも配慮が必要 マークやロゴは、名刺や封筒をはじめ、診察券、薬袋、院内・院外サイン(案内表示)、ホームページや車両、看板など、さまざまなアイテムと場面において活用されます。このため、ロゴとマークの組み合わせ基準や大きさなど、それらすべてに配慮したデザイン・マニュアルが必要となります。
もちろん、今回ご紹介したポイントに注意しながらロゴやマークをつくったからといって、すぐに「ブランドイメージ」が確立されるというものではありません。 |


 色を反転させてもイメージが弱くならない例
色を反転させてもイメージが弱くならない例