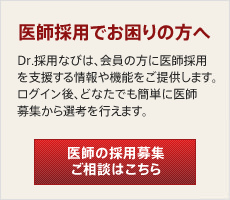|
はじめに
クリニックなどの医療機関にとって、ホームページは特に重要な広報ツールであることは誰もが認めるところでしょう。地域とのつながりがより強い開業医さんの場合、特に“口コミ”という評判が大切であることは今も変わりませんが、現在ではその“口コミ”さえもネット上で交わされていることは、既にご存じのとおりです。
このように、医療機関にとって欠かすことのできないホームページですが、広告などとは異なり、医療機関のホームページそのものには、具体的な規制がほとんどないのが実情でした。ところが今回、厚生労働省から「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)」(以下、ガイドライン)が発表(2012年9月28日)され、医療機関のホームページに初めて一定の規範を設けることとなりました。
今回はそんなガイドラインの中身について、具体的に考えてみましょう。
|
 |
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.ガイドラインが作成された理由は?
-----------------------------------------------------------------------------------------
自由診療に関する相談・トラブルの増加に対応
インターネットの急速な普及により、ますます多くの人がインターネットを利用して医療や健康に関する情報を得ています。当然、利用したい医療機関を探す際に利用される場合も多いのですが、その結果、全国の消費者センターには美容医療サービスや歯科インプラント治療などの自由診療を行う医療機関に関する相談が数多く寄せられるようになりました。
相談内容の具体例としては、「ホームページに掲載されている治療内容や費用が、実際に利用してみると違った」「事前の説明と、実際の対応が異なった」といったことがあります。
このため、国民生活センターなどからは国民・患者の利益保護の観点から、医療機関のホームページにおける不適切な表示などへの対応が求められるようになり、こうした状況をふまえて作成されたのが今回のガイドラインなのです。 |
|
医療機関の自主的な取り組みの規範
今回のガイドラインは、厚生労働省が設置した「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」による、5回にわたる検討会を経て出された報告(平成24年3月)を受けたものです。

つまり、今回のガイドラインはすべての医療機関が対象ですが、特に規制したいのは、誇大広告と思われる情報を掲載している自由診療を行っている医療機関の一部です。 また、その運用は自主努力とされているため法的拘束力はなく、例えガイドラインに違反していても、法的な処罰の対象となるものではありませんが、目に余る場合は公的機関から指導が入ると思われます。
|
-----------------------------------------------------------------------------------------
2.ガイドラインの中身は?
-----------------------------------------------------------------------------------------
|
ガイドラインは「ネガティブリスト」
今回のガイドラインは、トラブルを未然に防ぐことを目的に作成されたため、その中身はホームページに“掲載すべきでないもの”を例示した、いわゆる「ネガティブリスト」となっています。また、特に自由診療を行う医療機関を意識しているため、自由診療を行う医療機関だけを対象に、“掲載すべきもの”も示されています。
|


※黄色字は、以下に具体的な解説があります。
*厚生労働省「医療機関ホームページガイドライン」より
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002kr43.html
|
特に気を付けるべきポイントは?
それでは、今回のガイドラインを現在の各医療機関のホームページと照らし合わせた時、特に何に気を付けなければならないのでしょうか。
それぞれの医療機関では、少しでも新しい患者さんに利用してもらい、従来の患者さんも安心していただけるよう、ホームページを利用してさまざまな情報を発信されていることでしょう。
そこで、医療機関のホームページでもよく見かける点について、具体例を示しながら考えてみます。
※以下にある〔見解例〕とは、東京都(福祉保健局医療政策部医療安全課)に問い合わせた際の見解であり、必ずしも全国一律に適用される見解ではありません。
●「○○手術件数県内1位」はNG
最近、雑誌などでもよく見かける「ランキング○○位」ですが、たとえそれが事実で雑誌に掲載されたとしても、「他の医療機関よりも優位である」ことを示すものとして掲載できません(上記の「掲載すべきでない事項②」)。
ガイドラインではこの他、「日本一」「№1」「最高」などの表現も使うべきではないとしています。
〔見解例〕
許認可済みの医療機器を県内で初めて導入した場合、「県内初の導入」という表現は“不当な誘因”とは考えにくく、むしろ患者さんにとっては“医療機関を選択する際の重要な情報”となり得るので問題なしと考える。
●「医師数○○名」の表記は注意!
ガイドラインは「意図的に古い情報を掲載する」ことを戒めています(掲載すべきでない事項③a)。 これは、かつては多くの常勤医がいたが、今では常勤医が少なくなり非常勤医が多いのに、あたかも常勤の医師が充実した医療機関であるかのように見せるため、わざと正確な数字に直さないといった事例を意識したものです。 そこで注意したいのが、長く情報を更新(修正)できていないだけで、故意ではないのにわざと修正せずにいると誤解される可能性もあるという点です。
このため、今回のガイドラインに関わらず、定期的に正確な情報に更新することが重要です。
●治療前・治療後の“画像の並列”はNG
医療機関のホームページでは治療の効果を示すため、治療前・治療後の写真を並べて載せていることがよくあります。ところが今回のガイドラインは、誤解により不当に誘引するおそれがあるものとして、掲載すべきでないとしています(掲載すべきでない事項③b)。
これは特に、美容整形における“加工・修正した術前・術後の写真”を並べて、治療効果を強調した事例を規制することが目的ですが、加工・修正していない写真でも掲載不適と見なされる可能性があり、一般診療の医療機関でも注意が必要です。
〔見解例〕
加工・修正していない画像を使い、“あくまでも例であり、すべての人に同じ効果が期待できる訳ではありません”と注意書きを入れたとしても、患者さんは画像のような効果を期待し誤解を与える可能性があるため、自主的に慎むべき。

治療前 治療後
●褒めことばだけの体験談はNG
利用者へのアンケートなどによる“利用者の声”を掲載したホームページもよく見かけますが、医療機関に対して良いイメージを連想するような感想だけを取捨選択して掲載することはできません(掲載すべきでない事項③c)。
ただし、改善要望やクレームなどの感想も掲載した場合や、実施したアンケート結果が、すべて褒めことばだったので掲載した場合などは、ガイドラインには抵触しないと解釈できます。
●「キャンペーン実施中!」はNG
これも、特に自由診療を行う医療機関で目にすることがありますが、「期間限定で○○療法を50%オフで提供しています」「○○治療し放題プラン」などの表現は、早急な受診をあおり、費用の安さを過度に強調するものとして表示できません(掲載すべきでない事項④)。
また、「顔面の○○術、1か所○○円」とホームページに掲載されていたのに、実際に利用してみると、実は5箇所以上での価格で、「1か所なのに表示額よりもかなり高い費用を払わされた」といったトラブルがないよう、たとえ小さな文字で注釈があったとしてもNGとされています。
同時に、特に費用に関しては“掲載すべき事項”のひとつとして、ガイドラインに明示されています。
●「院長ブログ」は要注意!
自由診療に限らず、一般診療のクリニックなどにおいても「院長のブログ」「院長facebook」などはよく見かけます。こうした個人のブログなども、場合によってはガイドラインの対象となります。
ガイドラインの対象となるのは、院長として勤務している医療機関のホームページにリンクやバナーが貼られている場合です。こうした場合には医療機関のホームページと一体的に運用されていると見なされ、ブログに掲載されている内容も“掲載すべきでない事項”の対象となります。

|
-----------------------------------------------------------------------------------------
3.ホームページを見直す絶好の機会!
-----------------------------------------------------------------------------------------
|
先にも述べたとおり、今回のガイドラインは自由診療における行き過ぎた表現に一定の歯止めをかけ、まずは自主的な改善を促すものですが、一般診療を行っている医療機関についても、自院のホームページの掲載内容を見直せる絶好の機会です。
先の「特に気を付けるべきポイントは?」では東京都の〔見解例〕もご紹介しましたが、ガイドラインもホームページに掲載されているすべての内容を客観的にその適否を判断できるものではなく、同じ事例でも都道府県や各保健所の担当者レベルで見解がやや異なることも考えられます。
このため、ホームページをリニューアルするような場合や掲載してもよいかの判断に迷うような場合は、所管の保健所に問い合わせて、掲載内容に問題がないか確認してもらうと安心です。
一般診療のホームページの場合は、今回のガイドラインと照らし合わせて大幅に修正する必要がある、ということはあまりないと思いますが、案外“掲載内容がかなり古い”“最新の情報がまだ掲載できていない”ということに気付くものです。
この機会を利用して、「患者さんにとって分かりやすいか?」「利用者が必要としている情報が掲載されているか?」を第一に、必要に応じて情報を整理・追加・削除してみてはいかがでしょうか?
|