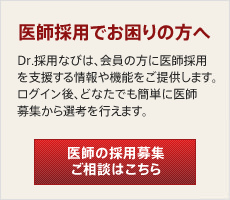Dr.採用なびは、医療機関の採用担当者向けのコミュニティサイトです。
- ようこそ!ゲストさん!
- ホーム >
- 利用者に読まれる広報誌づくり
2013.03.01
利用者に読まれる広報誌づくり
広報誌を発行する目的を明確に
東 昭吾(あずま しょうご)
NPO法人日本HIS研究センター 事務局員
株式会社ビジョンヘルスケアズ 社員

|
はじめに |
-----------------------------------------------------------------------------------------
1.広報誌を発行する目的を明確に
-----------------------------------------------------------------------------------------
| 広報誌を発行する目的と効果 医療機関における広報誌は大きく分けると、主に職員やその家族向けに発行される「院内誌」と、患者さんなど利用者向けとして発行される「院外誌」とがありますが、今回は地域への情報発信手段としても重要な院外誌について考えてみます。 広報誌を発行する目的とその効果についてまとめると、以下のような点があげられるでしょう。
まずは院内の体制づくりを 広報誌を発行する目的をはっきりさせるために必要なのは、まず、責任の所在をはっきりさせることです。つまり、職員の中から広報誌の担当者を決めるということです ある程度の規模の医療機関を除き、専属の広報担当者を置くことは現実には難しいでしょう。特にクリニックなどの場合、院長が広報誌を作っている場合さえあり、担当者がいても、ほとんどの場合が他の仕事との兼務なのが実情です。場合によっては、担当者が兼務のうえに一人しかいない場合もあります。 こうした場合、広報誌の発行を任されたものの、担当者は“あくまでも業務命令として指示されたから作っている”、という状況になりかねません。意識が低ければ、発行の目的を把握し、最終的に効果的な広報につなげることはまず無理でしょう。 まずは、担当者の人選が大切であり、責任者としての自覚と発行の目的をぶれないように把握させることが重要です。同時に、担当者一人に任せず、院内での意識を共有させるためにも、各部署などから選出された職員によってチームや委員会を編成し、職員全体を巻き込んだ活動にする必要があります。 一部の職員だけが認識している広報誌では、地域の方への認知度が上がるはずもありませんね。 |
-----------------------------------------------------------------------------------------
2.わかりやすい広報誌にするために
-----------------------------------------------------------------------------------------
|
読者にとって“わかりやすい広報誌”にしたいということは誰でも考えることでしょう。 では実際に広報誌を制作する場合、“わかりやすい広報誌”にするためには、何に気をつけるべきなのでしょうか。
実際の制作でのアドバイス 担当者がスケジュール通りすすめようとしてもままならないのが、原稿集めでしょう。「先生に頼んだけれど、なかなか提出してくれない」。これは担当者に多い悩みのひとつです。ただ、ちょっとした準備、配慮で、そうした問題を解決できる場合があります。
「誤字脱字のチェックだけならともかく、読みやすい文章にするための“校正”なんて経験がない」という職員も多いでしょう。そこで、読みやすい文章にするためのちょっとしたコツをご紹介します。
「わかりやすい文章が書けた」と思っても、実際に読んでもらえないと、わかりやすいかどうかもわかりません。人は誰でも、特に興味がない限り、文字だけがびっしり詰まった黒々としたレイアウトでは、読みたいという気持ちがおこりづらいものです。その一方で、無秩序にイラストの多用・デザイン過剰なレイアウトでは、読み手のストレスや目の疲労にもつながりかねません。 効果的な写真やイラストの配置にも注意しましょう。
ただ、実際には多忙な毎日において、院内だけですべてを完成させるのは非常に困難で、分かりやすさも実現するためには、何といっても経験がものをいいます。 【わかりやすい広報誌の実例】 (NPO法人日本HIS研究センターが主催する“2012HISデザイン賞”受賞作品より)
■大賞 受賞作品 『ともに生きる』 「構成が秀逸でスッキリとまとまっている。本文の文字サイズや組版も読みやすい」 ■優秀賞 受賞作品 『ひまわり』 他の入賞作品も下記より確認できます。 |
-----------------------------------------------------------------------------------------
3.広報誌発行の波及効果
-----------------------------------------------------------------------------------------
|
WEBやイベントとの連動 自院のホームページに広報誌のPDFをアップしている医療機関は増えています。 ただ、いくらその病院に好きな先生や看護師さんがいたとしても、“一生病院で治療や診察を受けていたい”と考える人はいないでしょう。ということは、広報誌を手にするのは、連続して発行していてもその一部なので、バックナンバーも見られるという点は、利用者にとっても大きなメリットです。 ただ、先に述べたように、伝えたい情報を取捨選択し、限られた紙面に載せるということは、伝えたかったが伝えきれていない情報もまだあるはずです。こうした場合は、広報誌とホームページで情報をわざと分割し、広報誌には「さらに詳しいことをお知りになりたい方は…」といった表現を掲載して、ホームページで追加情報を補ってあげるとWEBとの連動という点でも効果的でしょう。 また、発行した時には間に合わなかったけれど、次の発行で載せるのは時期外れだという“旬がある情報”などは、予告的な情報だけを広報誌に掲載し、その結果やタイムリーな情報は積極的にホームページの更新情報として活用するとよいでしょう。 広報誌の効果も一日にしてならず もともと広報とは、乾いた地面に水がゆっくりとしみ込んでいくように、ゆっくりと、そしてジワジワと浸透していくものです。これは、医療機関にとって最も大切な信頼の醸成でもあります。 こう考えると、やはり広報誌の発行を含めた病院の広報は、継続した地道な活動が欠かせません。 まさに、古代ローマと同じように、医療機関の信頼獲得も“一日にしてならず”ですね。 |





.jpg?1385001882)